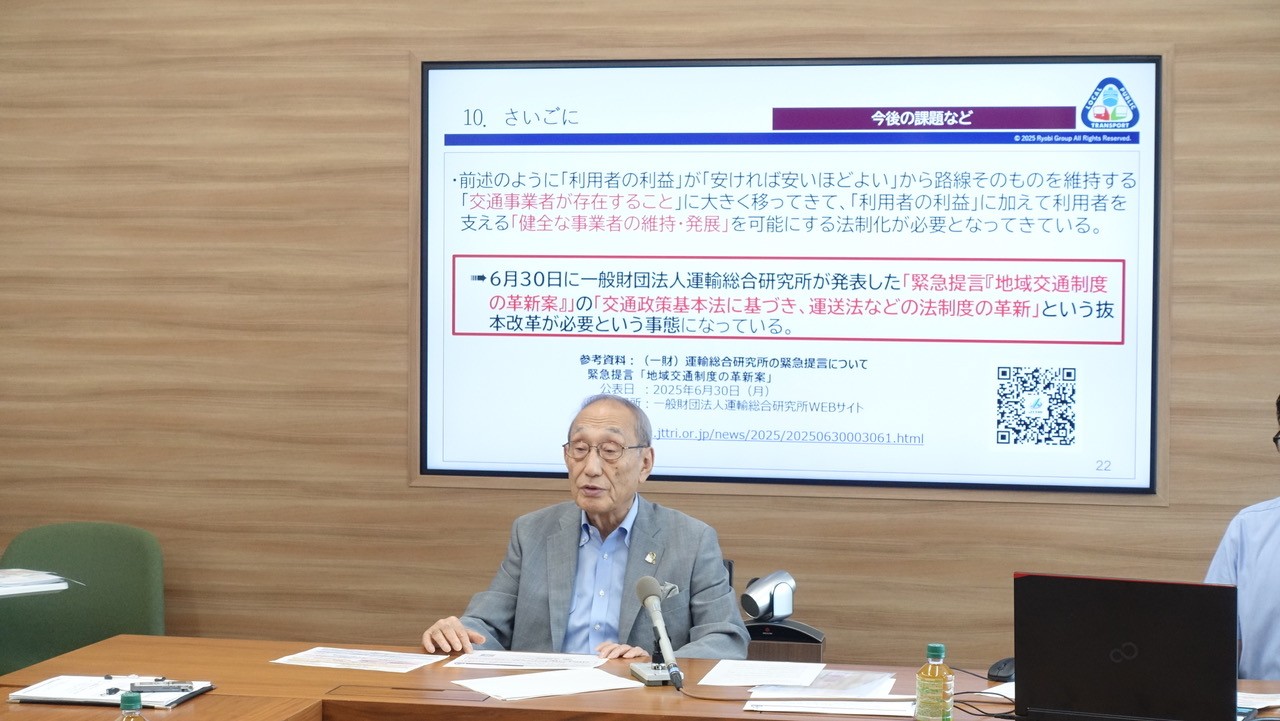地方交通は「危機」ではなく「危篤」状態か?
―運輸総研による「緊急提言」は地方交通を救える―
(一財)地域公共交通総合研究所
代表理事 小嶋光信
2025年6月30日、(一財)運輸総合研究所は、2023年の「地域交通産業の基盤強化・事業革新に関する提言」に基づき、「地域交通制度革新に関する検討委員会」による緊急提言として、「地域交通制度の革新案」を発表した。実にタイムリーな提言である。
現在、日本の地域交通は「危機」どころか、もはや「危篤」と言える深刻な状況にあるのではないか。
とくに地方の路線バスは、少子高齢化とマイカー依存により、30年以上にわたり赤字経営が続いてきた。そこに、100年に一度のパンデミックとも言われるコロナ禍が追い打ちをかけ、利用者が激減。感染拡大が収束した後も、乗客の約1割は戻ってこないままである。
さらに深刻なのが運転手不足だ。2024年に始まった労働時間制限、いわゆる「2024年問題」の影響もあり、必要な人員が確保できず、2023年度だけで約2,500kmもの路線が廃止された。これは、九州から北海道までに匹敵する距離である。
加えて、首都圏への人口集中は止まらず、地方の過疎化が進行。地域によっては交通サービスの維持が「困難」どころか、「絶望的」と言っても過言ではない。
なぜここまで悪化したのか──制度疲労と求められる緊急な政策判断
1990年代以降、日本では「競争こそがサービスを良くする」という考えのもと、規制緩和が進められた。交通事業も一般の民間ビジネスと同様に扱われ、参入・撤退の自由が認められた。その結果、採算の取れない地域ではバスや鉄道の路線が次々と廃止され、交通空白地が広がった。
事業者は過当競争にさらされ、収益が上がらないなかで運転手の賃金は低下し、人材確保が困難となった。本来、利用者にとっての「利益」とは、料金の安さだけではなく、必要なサービスが安定的に提供されることであることに、私たちは理解しなければならない。
制度疲労が進行した今こそ、「競争」から「協調と共創」への転換が求められている。
運輸総研の「地域交通制度の革新案」の内容は何か?
主な内容は以下のごとくだ。
1.目指すべき法制度のあり方
運輸総研は、以下のように提言している。
「国民生活の質(QOL:クオリティ・オブ・ライフ)向上の観点から、潜在的な需要も含めた『需要』に応える健全な事業の存立と、『供給』としての健全なサービスの確保・維持・改善を可能とする制度が必要である。そのためには、『交通政策基本法』に基づき、道路運送法・道路交通法・地域公共交通活性化・再生法をはじめとする地域交通関連のすべての法制度の革新が喫緊に必要である。」
つまり、規制緩和以降に大きく変化した社会情勢に対応するため、交通関連法制度そのものを「交通政策基本法」に則って抜本的に改革する緊急の必要があると指摘している。
2.法律に盛り込むべき具体的な事項
運輸総研は、以下の点を法律に明記すべきと強調している。
■ 地域交通を「公共財」として再定義
- 地域交通は「公共財」で「社会資本」であること。(~民間事業の自由競争に委ねていては実現できないサービス~)
- 地域交通の「確保責任主体」は自治体であること。地域ごとに「法定協議会」を設置することを義務化。
- 路線の開設・廃止などは、法定協議会の合意が前提。
- 必要なサービス水準は、国が「交通政策基本法」に基づいて明確化。
■ 財源は「補助金」から「委託の対価」へ
- 地域交通は自治体の確保責任に基づく「委託」により実現するものであることを明確化。自治体の地域交通への支出の根拠は、補助でなく「委託の対価」であることを明確化。
- 社会資本としての役割の確実な実現に必要・十分な財政措置の明確化。
- 地方交付税の地域交通充当額の明確化、国及び自治体の各分野の交通関連財源の一元化などを通じて、安定的な財源確保を図る。
3.緊急提言から読み解く改革の具体的な3つの柱
緊急提言からは、次の3つの具体的な柱をもとに制度改革を進めるべきことが読み取れる。
① 地域主導の体制づくり
法定協議会に大きな権限を与え、「地域のことは地域が決める」体制に移行する。
② 競争から協調へ
これまでの「競争前提」の制度を見直し、「協調と共創」に基づく制度設計によって、健全な事業者を育てる環境を整備する。利用者にとっての真の利益とは、安定したサービスを継続できる事業者の存在である。
③ 赤字路線への持続的な支援
私見として、黒字路線は引き続き民設民営で運営し、赤字路線は短期的には補助金で支えつつ、中長期的には公設民営や委託方式に転換することで、民間の経営努力を引き出す仕組みを整える。地方鉄道はすでに公有民営の制度が定着し、対応が遅れている旅客船事業も公有民営はなじみやすい。バスは投資額がそれほどでもなく現状の補助金制度の充実でという声もあるが、赤字補填は経営努力を生まない。今回の岡山市での支線の公設民営のように、赤字路線ごとの公設民営・民託は投下資本も小さく経営努力を引き出しやすいし、行政も毎年赤字補填するより効率的だ。
4.すでに成功している事例がある
私自身、これまで複数の地域交通再建に携わってきた。
- 津エアポートライン;公設民営を実証、数々の困難を乗り越える。
- 和歌山電鐵:地方鉄道で公設民営を実証し、公有民営の制度化に貢献。
- 井笠鉄道:公設民託のバス制度を開発し、コロナ禍でも安定運行を維持して黒字経営で切り抜け、運転手の確保にも有効と実証。
- 中国バス:労使協調を回復し、経営を効率化し、補助金を大幅に返上した実績も。
さらに、「四日市あすなろう鉄道」「養老鉄道」「近江鉄道」などの再建支援や、江田島市における海上アクセスの公設民営化など、数多くの事例がある。
これらの事例は、「努力すれば黒字になる」「働く人が報われる」仕組みさえ整えば、持続可能な交通サービスは実現できることを明確に示している。キャッシュレス化、デジタル化(DX)、EV・自動運転といった未来への投資も、黒字化の見通しが立てば一気に前進できるだろう。
おわりに
交通事業に関する運送法は「事業法」である。すなわち、健全な経営を支える法制度であり、真面目に経営努力すれば黒字化する事業でなければならない。
今、必要なのは「競争か規制か」という単純な対立ではなく、地域の実情に即した「需給の最適化」と、それを支える柔軟な制度改革である。
私は、これまでの実践と今回の運輸総研による緊急提言によって、地方交通の「危篤」状態からの回復は必ず可能だと確信している。今こそ抜本的改革を実行し、**「交通がある安心」**を全国に取り戻さなければならない。
そのためには──
運送法を時代に合った改正をし、交付税や暫定税率などから財源を確保すれば、この地域公共交通の危篤状態から脱することが出来る。すなわち、
「交通政策基本法に則り、交通を公共財・社会的共通資本として位置づけ、運送法を改正する。そして、19兆円の地方交付税の約1%を交通関連予算として上乗せし、地域交通特別交付金(仮称)等として別枠で年間2,000億円程度を確保する。赤字補填の補助金は短期支援とし、公設民営・公設民託を中長期的な対策とすることで、民間が経営努力により黒字化を目指せる夢のある制度設計が可能になる。」と結論付けられる。
この緊急提言こそ、日本の地域交通を維持・発展させる最後のチャンスである。地域交通を心配する市民、行政、そして政治が一体となって、
「抜本的改革で運送法などを改正し、公共交通を取り戻そう!」
と、大きな声をあげ、ともに夢のある新しい時代を切り開こうではありませんか!
2025.7.28.
参考資料:緊急提言について
「地域交通制度の革新案 【緊急提言】 」
公表日 :2025年6月30日(月)
掲載場所: