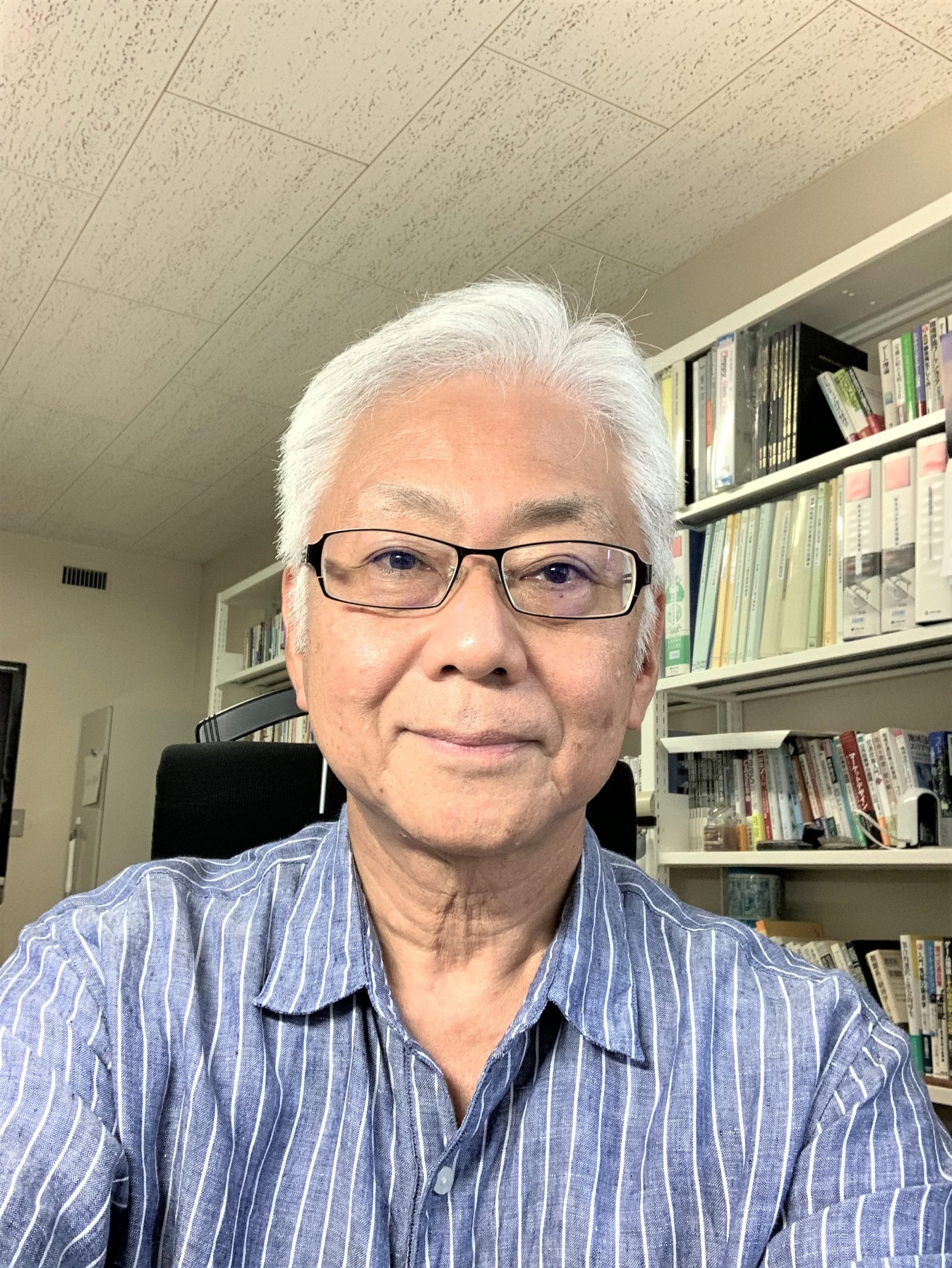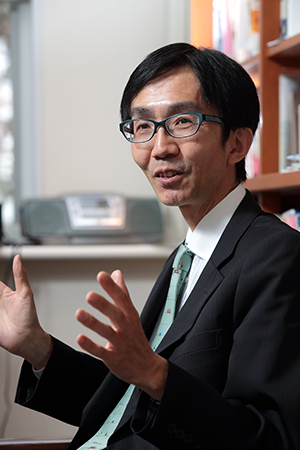京都大学公共政策大学院では、国土交通行政を題材に行政学的な課題や行政の現場の実態を語るとともに、地域公共交通政策をケーススタディーにゼミ形式の授業を受け持って学生が選択した地域の公共交通の現状と改善策を共に学び議論しています。 地域の公共交通は、モータリゼーション、規制緩和、人口減少などにより厳しい状況にありますが、住...
地交研の概要
Category
モータリゼーションの進展や人口減少に伴う公共交通需要の伸び悩みなどを背景に、これまでも多くの地域交通事業者が厳しい経営を余儀なくされてきました。さらに、2000年代前半の規制緩和により高収益路線等に過当競争が生まれ、コロナを契機とした移動需要の変容がさらなる打撃を与えたと認識しています。 一方で、近年は地域公共交通が地...
■所見 岡山大学で都市・交通計画の研究をしています。これまでは、トヨタ自動車系シンクタンクで15年、東京海上G系シンクタンクで15年と、複数の角度から自動車交通にかかわってきました。この度、岡山という“私の新しい地元”で、これまでの経験も活かしながら、長期スパンやグローバルといった少し広い視座で、地域公共交通のあり方の...
地域公共交通総合研究所のアドバイザリーボードメンバーとしての私の使命は、日本とヨーロッパの都市モビリティのそれぞれの課題に対する理解を深め、実現可能な解決策を見出すのに貢献することです。また、日本と欧州の関係者の間でグッドプラクティスや研究成果を共有することで、両国の持続可能な都市モビリティのあらゆる側面における協力関...
コロナ禍を経てわが国の公共交通が「危機的」な状況である。しかしこの「危機」は、本質的には従来から変わらぬ制度を前提とし、しかもコロナ禍前からくすぶっていた公共交通「事業」の危機が露呈したものである。公共交通機関が市民に忌避されるようになったわけでもなければ、安全で効率的な運行や運営の技術が廃れたわけでもない。 ところが...
地方都市では、過度な自動車依存による公共交通の衰退や市街地の低密度化などの課題に適切に対応し、将来世代に責任の持てる持続可能な社会を構築することが求められています。 私は富山市長として2003年以降、「自動車利用を中心とした従来の拡散型のまちづくり」から大きく方向転換し、「公共交通を軸とした拠点集中まちづくり」を目指し...
.dp_sc_prof_desc { min-height: 130px; } 理事 評議員 監事 顧問 アドバイザリー・ボード委員 研究員
熊本市では、民間3バス事業者の経営不振と市営バス事業の民間移譲を契機に、2008年~2011年の「バス輸送のあり方検討協議会」、2012年からの「熊本市公共交通協議会」での熱い議論の成果として、我が国では例を見ない先進的な公共交通の再デザイン案が提案され、順次実装されてきました。たとえば、公共交通基本条例の策定、自主運...
コロナ禍の下、地域公共交通が非常に厳しい状況にあることは、本研究所の調査でも明らかですが、人口減少や高齢化、地球環境問題を考えたとき、地域公共交通の制度が右肩上がりの時代のままであることに問題の根本があります。 本研究所は、大都市圏にある通常のシンクタンクとは異なり、地域に根差し、現場の実務に精通した研究員が、地道な調...
今次、アドバイザリー・ボード委員への再度の就任にあたり、前職の日本政策投資銀行時代の視座だけでなく、海事政策の観点も含め海上交通等の在り方等に着目して取り組んでいきたいと考えています。コロナ禍が続くものの、2025年大阪万博が予定されるなかでは、インバウンドの本格的な再開とともに今後の観光資源として期待が高まる瀬戸内海...